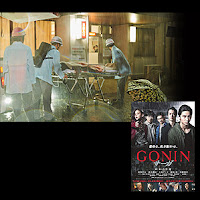石井隆に最初に触れたのは、図書館の書棚を介して、映画監督実相寺昭雄の著書(*1)に載った数点の挿画だった。発売から少し経っていた。単行本がその時点で何冊も書店に並んでおり、独自のスタイルを確立して色香がより増した【黒の天使】(1981)を雑誌に連載中なのだった。以来愛読者のひとりとなった訳だけど、つまり、わたしは石井劇画が平穏な日常に突如出現し、それが鎌いたちのように世間を切り裂いてどれほど大きな衝撃をおよぼしたか、彼のデビュー当時の目撃体験を全く持たない。この事につき悔しく、残念に思うときがしばしばだ。
人が実際に感じ切ったその時どきの微妙な気配というものは、その人限りに宿るのであり、後世の誰彼に譲ることは出来ない。全宇宙で唯一無二のものだ。政情の変化や衆意の斜度、戦争との距離はいかばかりで、道ゆく人の頬に弛緩があったのか緊張が走っていたものか、鼻腔に飛び込むのは薫風であったか不潔臭だったか。いかに達筆な文章を読んでも、そんな時代感覚までも残らず共有することは相当に困難だ。他人の体験はどう足掻いたって自分のものとはならない。
だから、石井隆の過去作を私がいくら探し求めて読んでみても、当時の世間の熱狂を知ることだけは絶対に叶わないし、それが石井という作家にどんな具合に創作意欲を湧かせ、同時にどのような失望を与えたか、そしてそれ等が作風にどんな影響を及ぼしたか、この点を踏まえた俯瞰なり解読がならない。きわめて大切な部分と思うが、ここは山根貞男か権藤晋にでも託すしか道はないだろう。
石井のかつてのホームグラウンドは「ヤングコミック」であったのだが、同誌に関わる本が最近出されており、目で追いながら歯がゆい思いを抱いた。いずれも別の作家、手塚治虫と上村一夫(かみむらかずお)をめぐる本であり、世代的に、加えて嗜好的に両者に対する興味と憧憬は以前から強くある。また、ふたりの名はインタビュウ中で石井の口から度々出てもいる。彼らを知ることは石井を知ることに繋がるように信じているから、頁をめくる毎に喜びが寄せては来たのだけれど、リアルタイムの熱狂を知らぬもどかしさは解消ならず、渇きは癒されるとは逆に増すばかりであって実に困った。生まれるのが少し遅かったように思う。
二冊とも“少年画報社創業70周年記念”と謳っている。ひとつは「鉄腕アトムの歌が聞こえる ~手塚治虫とその時代~」(*2)であり、編集者として時代の先端を歩んだ著者橋本一郎が体感した手塚プロダクションの盛衰と作家の苦闘の様を中軸とし、加えて漫画およびアニメーションのキャラクタービジネスの黎明期をつぶさに描いてみせた労作である。勢いのある筆致に胸を躍らせて読み進めた。金脈を探し当てるのは常に若い情熱であり、そのほとんどが世間の目の触れない場処での泥だらけの採掘と知る。数々のエピソードを通じて苦労がじわりと伝わって、今更ながら頭が下がる思いがした。
橋本は「増刊ヤングコミック」の編集者として、その頃まだマイナーであった石井隆の作品、具体的には【埋葬の海】(1974)の再録を同人誌に見つけて唸り、彼を登用し、その後の石井の劇画人生、そして映画作家としての新たな幕を切って落とした人だ。当時の熱狂を懐旧して以下のような文章を綴っている。創り手側に起きたどよめき、震動が感じ取れる貴重な証言となっている。
私がかわぐちかいじの仕事場にあった同人誌『蒼い馬』で見つけた鬼才、石井隆が、増刊にデビューすると、読者ばかりでなくマンガ家、編集者、作家、評論家、映画関係者にも想像を絶する衝撃を与えました。彼のみずみずしく豊潤な情感を流し込んだ作品によって、(中略)劇画は革命的に一変し、部数は右肩上がりになりました。それは私にとってたまらない快感でした。(315頁)
想像を絶する、革命的に一変、という表現ふたつを、石井世界を愛する者は記憶に刻んでおくべきだろう。
もう一冊は「ヤングコミック・レジェンド 上村一夫表紙画大全集」(*3)であり、1969年の夏から1980年の春までの10年以上に渡って描かれた上村の表紙画を紹介したものだ。上村のおんなの造形に惹かれる者にとって、絶対に見逃せない内容となっている。該当する号の幾つかを購入し、また、新宿早稲田の現代マンガ図書館で眺めてもいるが、こうして一堂に会した姿というのは壮観であるし、方角を石井とはまるで違えてはいるが、おんなという存在を終生にわたって凝視め続け、筆の先に探し求めた上村という男の鼓動や血流が感じ取れるようで胸に迫るものがあった。
技法に関する記述としては、これら表紙の構図やテーマ、そして配色に関して編集部(筧悟、岡崎英生ら)とデザイナーも加わっての共作であった点も分かり、視野がぐんと広がった。美女画と共に題字も活き活きと配され、今見ても新しく感じる箇所が多い。現在の書籍の表紙にはホログラフや擬似エンボスが溢れ返り、写真製版も完成された観を呈しているが、70年代には手法も技法もまるで手探りであったわけで、毎号が冒険に次ぐ冒険、掟破りの連続だったことだろう。新しい表現を模索する出版人の息吹き、まなじりが確かに感じ取れるし、商品デザインに関わる人には示唆に富む内容かと思われる。
石井に関する記述は無いに等しいのだが、掲載された全260枚の表紙が世に出た時期と、石井劇画が「増刊ヤングコミック」からこの「ヤングコミック」本誌にも活躍の場を広げ、名作を創出した時期とは重なるところがある。だから題字の扱い方を目で追っていくと石井作品への読者の支持がどれだけ急激に、巨大に膨らんだのか理解出来るところがあり、その点で貴重な資料となっている。
1975年夏の初登場からして目立っているのだが、直ぐに題字のポイント数が上がり、置かれる場所もトップポジションとなり、【天使のはらわた】が映画化されると別格扱いとなった。1979年6月27日号では【おんなの街】の連載開始を大々的に報せて、何と作者名と題字は「ヤングコミック」という誌名とほぼ同じ大きさで組まれていて物凄い。
こうして自身の筆名と自作のタイトルが大きく取り上げられる恍惚と圧力はどれ程のものだったろう。また、そのような神輿(みこし)に担ぎ上げられて後、通常の扱いへと戻された時の淋しさと焦りはどれほどのものだったろう。才能がない自分には無縁のことだし想像のしようがないのだけれど、いまだに人気漫画作家の幾たりかはその後の空虚さに耐えかねて自らの命を断っている訳で、創造を糧とする者、人気商売に関わる者に襲いかかる牙は全く容赦がなく、凄惨この上ないと感じる。
石井隆という作家を考えるとき、わたしは常に「ヤングコミック」登場時の大きな波を思い描き、その水圧や高低差がどれほどだったかを懸命に手探る。これに耐え抜き、今も泳ぎ続けているしぶとい泳ぎ手として、いまの石井を捉える。暗礁に叩きつけられ、塩水を呑み、砂を噛む思いをどれだけしただろう。彼のドラマに常ににじみ出る苦労人のまなざしは、こういった背景に醸成されたのではなかったか。
なにくそ、なにくそ、と懸命に水をかく石井の背中を思うと、自分も負けられないという気持ちが自然と湧いてくる。そういう息の長い作家を偶然知ることが出来たことは、私たちにとって何よりの幸せであるように思う。
(*1):「闇への憧れ―所詮、死ぬまでの《ヒマツブシ》」 実相寺昭雄 創世記 1977
(*2): 「鉄腕アトムの歌が聞こえる ~手塚治虫とその時代~」 橋本一郎 少年画報社 2015 ウェブで知己を得た手塚ファンがいて、彼の書き込みから著者の経歴と本の内容を教わった。これを読んでくれていたら、感謝です。教えてくれてどうも有り難う。
(*3): 「ヤングコミック・レジェンド 上村一夫表紙画大全集」 少年画報社 2015